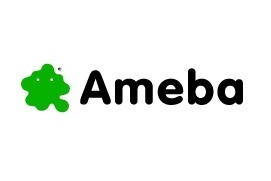横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。

Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office
神奈川県横浜市戸塚区名瀬町765-8-706(最寄駅:JR東戸塚駅)
対応地域:横浜市・川崎市その他神奈川県全域・東京都全域
英語でも対応可能
代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。
横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記
まもなく消費税の軽減税率がスタートします
皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。
いや~、昨日の台風は本当にすごかったですね。久しぶりに台風が関東地方を直撃したような気がしますが、千葉県や神奈川県を中心に大きな被害がでたようです。しかも、翌日は首都圏の交通機関が1日中、麻痺するという事態になりました。
何せ電車がぜんぜん動いてないものですから、うちの事務所の周りの道路も夕方頃まで、ずっと渋滞していましたしね。
勤め人だった頃は、こういった台風や大雪で交通機関が麻痺したときでも、何がなんでも会社へ行かなきゃという雰囲気がありましたが、今は自由な身であるため、台風や大雪のときに満員電車のストレスに巻き込まれることもなく、こういったことも自営業者のメリットと言えばメリットですね。
さて、来月10月1日から2度にわたり延期されてきた消費税の増税がついに行われることになります。
消費税の増税とともに、日本では消費税が複数税率(10%・8%)になるのも初めてだと思いますので、本日は、改正消費税について簡単にまとめてみたいと思います。
【軽減税率の対象となる商品について】
10月から消費税の税率は、10%になるわけですが、一部の商品は8%のまま据え置かれることになります。その商品とは主に飲食料品と新聞です。
飲食料品について、大事なポイントとして次のことは覚えておきましょう。
・飲食料品(酒類を除く)を持ち帰る場合には、8%
・飲食料品(酒類を除く)を場所を提供してもらい飲食できる場合には、10%
もっと簡単に言うと、うちで食べれるなら 8%、外で食べれるなら 10%。これが大原則です。
次に新聞について、大事なポイントとして、週2回以上発行される政治や経済面などの記載のある新聞としていますが、次のように覚えておきましょう。
・毎日、家や会社に配達してくれる新聞は、8%
・駅の売店やコンビニで購入する新聞は、10%
最近では、新聞や本をネットで見ることもできますが、この場合の新聞は、新聞じたいを配達してもらっているわけではないため、10%として取り扱います。
【売上についての注意点】
売上については、やはり軽減税率が生じる可能性の高い業種(スーパー、コンビニ、デパート、外食産業(ファミレス、ファーストフード、食堂など)、酒屋、パン屋その他の飲食料品を扱う店舗および新聞屋)は、気をつけなければなりません。
だけど、上記の業種でレジを打ったりする現場で働く人って、たいがい学生や主婦、外国人などのアルバイトやパートの割合が高い業種が多いと思いますので、レジの打ち間違えとか大丈夫かな~、と個人的には気になるところです。
で、上記の業種の場合の経理処理ですが、下記のように、税率が異なる商品ごとに、わけて記帳するようにします。8%と10%の商品をまとめて記帳するとあとで見たときにわからなくなりますので、注意しましょう。
正) 現金預金 2,180 / 売上(8%) 1,080
/ 売上(10%) 1,100
誤) 現金預金 2,180 / 売上 2,180
また、10月以降は請求書や領収書などにも、10%と8%の商品を区別できるように表示し、8%の税率の商品については、「軽減税率対象品目」などと記載し、10%の商品と区別できるようにしなければなりません。
なお、上記以外の業種の場合は、10%のみの税率という場合も多いと思いますので、10%の税率のみの業種の場合には、区別の必要がないことから、請求書や領収書などに「軽減税率対象品目」などと記載する必要はありません。
あと、今回の増税に伴い令和5年10月1日から税務署から発行された登録番号を請求書や領収書などに記載するインボイス制度が始まります。
令和5年10月1日までに税務署から登録番号の発行を受けるためには、令和3年10月1日から令和5年3月31日(やむを得ない事情がある場合には、令和5年9月30日)までに、事前に税務署に登録申請をしなければなりません。
税務署から登録番号の発行を受けたり、請求書等への登録番号の記載は義務ではありませんが、取引先に事業者(法人、個人事業主および不動産貸付業者)がいる場合には、消費税の仕入税額控除(消費税における経費)を受けるため、登録番号の入った請求書や領収書などの発行を求められる場合があります(登録番号の入った請求書等の発行を取引先に求められた場合には、発行する義務があります)。
しかも、税務署から登録番号の発行を受けた場合には、売上が1,000万円を超えているかどうかにかかわらず消費税の申告と納付義務が生じます。
これは消費税の免税という制度を残しつつ、売手か買手のどちらかに免税事業者の消費税を負担させることを意味しています。
取引先が100%、一般消費者のみで事業の経費にする可能性がない業種(病院、学習塾、結婚相談所など)の場合には、一般消費者が登録番号の入った請求書や領収書などの発行を求めることはないと思いますので、税務署から登録番号の発行は受けなくてもいいと思います。
【経費についての注意点】
経費については、福利厚生費、交際費、会議費および新聞図書費などの勘定科目で10%と8%の税率が混在する可能性がありますが、売上の場合と同様に、請求書や領収書などに10%と8%の商品が混じっている場合には、下記のように必ず区別して記帳するようにしましょう。まとめて記帳すると、後でわからなくなります。
正) 会議費(8%) 1,080 / 現金預金 2,180
会議費(10%) 1,100 /
誤) 会議費 2,180 / 現金預金 2,180
レシートであれば8%と10%の区別ができていると思いますが、手書きの請求書や領収書を受領する場合で、軽減税率の対象となる商品を購入する場合には、必ず「軽減税率対象品目」と記入してもらい、10%の税率の商品と区別できるようにしましょう。区別できない場合には、すべて10%の税率として取り扱われてしまいます。
なお、消費税で簡易課税を選択している場合には、売上をもとに消費税額を算出しているため、本来は経費も区別して記帳しなければなりませんが、まとめてしまっても、消費税の計算には影響しないと思います。
また、簡易課税を選択している場合でも、売上が5,000万円を超える場合には、経費の消費税の実額により消費税を計算する原則課税という方法で計算をしますので、この場合には、経費の記帳を、8%と10%できちんと区分しておく必要があります。
令和5年10月1日以降は、支払先から必ず、税務署から発行された登録番号の入った請求書や領収書を受領するようにしましょう。
法人税や所得税では、事業上の経費は経費にできますが、消費税では令和5年10月1日以降、登録番号の入った請求書や領収書を保存していない場合には、消費税の仕入税額控除(消費税における経費)を受けられなくなる可能性があります。
【ポイント還元についての注意点】
消費税の増税に伴い令和元年10月1日から令和2年6月30日までの9ヶ月間の期間限定でポイント還元が行われます。クレジットカード、電子マネー、QRコードなどの現金支払いを伴わない一部の商品の購入で、5%または2%のポイントが付与されます。
ポイントが付与されたときは、特に会計処理は生じませんが、ポイントを使用したときにいくつかの会計処理があります。
・支払額で経理処理する場合
消耗品費 980 / 未払費用 980
・ポイントを値引きとして経理処理する場合
消耗品費 1,000 / 未払費用 980
/ 消耗品費 20
・ポイントを収入として経理処理する場合
消耗品費 1,000 / 未払費用 980
/ 雑収入 20
上記のいずれで経理処理をしたとしても利益には影響しませんが、税務上の判定に影響してくる可能性があります。
今回の改正により消費税はややこしくなってしまい、かつ、作業が面倒になってしまうことには間違いありませんが、決まってしまったことなのでしかたがありません。参考にしていただければ幸いです。
本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。