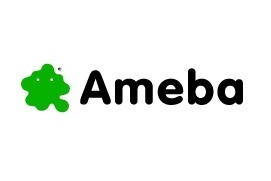横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。

Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office
神奈川県横浜市戸塚区名瀬町765-8-706(最寄駅:JR東戸塚駅)
対応地域:横浜市・川崎市その他神奈川県全域・東京都全域
英語でも対応可能
代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。
横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記
消費税のインボイス制度の登録申請が始まりました
皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。
新型コロナウイルスの感染者数が、いい感じで減少してきていますね。このまま収束してくれると嬉しいのですが、今年のコロナ感染のピーク時期は、昨年と同じように推移していますので、今年11月あるいは12月頃から来年2月頃にかけて、再度、感染者数が増加する可能性もあります。やっぱり感染者数が減少してくると、これまでと同様にマスクはしていたとしても、気分的には緊張感がやわらいできているような気がしますが、今年の年末年始頃の感染状況によって来年の感染状況や経済状況は変わってくると思いますので、引き続き緊張感をもって感染対策をおこなっていきたいものです。
さて、本日ですが、実際に実務として運用されるのは2年後なのですが、今月10月1日から消費税のインボイス(適格請求書)制度の登録申請が始まりました。
まだ、少し先のことなのですが、知っておいてもいいと思いますので、本日は消費税のインボイス制度の3つの注意点について、お伝え致します。
まず、インボイス制度の登録申請なのですが、実際に運用される前に税務署から登録番号を発行してもらうための登録申請を、原則として、令和3年10月1日~令和5年3月31日までの期間に行わなければなりません。うちの事務所では、あまり早く登録申請をしてしまっても、忘れてしまったり、登録番号(登録通知書)を紛失してしまう可能性もありますので、下記の登録申請書を、令和5年2月~3月頃に、まとめて提出する予定です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0020009-098_04.pdf
なお、登録申請をおこなう場合には、令和5年10月1日以降、下記の3点について注意が必要になります。
1.売上の請求書等に税務署から発行された登録番号を記載しなければならない
売上のわかる書類(請求書、領収書や契約書など)には、税務署から発行された登録番号を記載しなければなりません。
細かく記載事項が定められていますが、現在と大きく異なるのが、登録番号を請求書等のどこかに記載することです。
なお、インボイス制度の適用につきましては強制ではありませんが、取引先に事業者(法人・個人事業主および不動産貸付業者)がいる場合には、下記2の理由から相手先から登録番号入りの請求書等を請求される可能性があります。
とくに売上が5,000万円を超える取引先の事業者がいる場合には、消費税の計算方法が原則課税(実際の売上の預かった消費税から経費の支払った消費税を差し引いて消費税を計算する方法)のみで計算されますので、取引先から登録番号入りの請求書等を請求される可能性は大です。
2.経費の支払先から税務署から発行された登録番号入りの請求書等を入手して保存しなければならない
令和5年10月1日以降、経費に対する消費税の取り扱いにつきましては、次のとおりとなります。
・支払先から登録番号入りの請求書等(請求書、領収書および契約書など)を入手し、保存している場合
これまでと同様に、消費税の計算上、消費税のかかる支払いとして認められます。
・支払先がインボイス制度の適用事業者でない場合やインボイス制度の適用事業者ではあるものの登録番号を請求書等に記載していない場合
この場合、令和5年10月1日以降、支払先に消費税を支払っていても、消費税の計算上、消費税のかかる支払いとしては認められません。
つまり、会費、保険料、支払利息などのように消費税のかからない経費として取り扱い、消費税の計算をおこなうことになります。
そのため、スーパーやコンビニなどのいわゆるレシートにつきましては、令和5年10月1日以降、登録番号は印字されていると思いますが、手書きの請求書や領収書を受け取った場合で、登録番号が記載されていない場合には、必ず相手先に登録番号入りの請求書や領収書等を発行してもらえるかどうかの確認をおこなってください。
令和5年10月1日以降、会費、保険料、支払利息のような本来、消費税のかからない取引については、必要ありませんが、消費税のかかる支払いにつきましては、登録番号入りの請求書や領収書等を保存していない場合、消費税の計算上、不利な取り扱いをうける場合があります。
なお、消費税の計算方法を簡易課税(実際の売上に業種に応じて定められているみなし仕入率を乗じて消費税の仕入税額控除を計算する方法)で選択している場合には、実際の経費の支払った消費税で仕入税額控除を計算しないため、支払先から登録番号入りの請求書等を入手して保存しなくてもかまいませんが、売上が5,000万円を超えてしまいますと簡易課税を選択していても、原則課税のみで計算しなければならないため、やはり支払先から登録番号入りの請求書等を入手し、保存しておいた方がいいでしょう。
また、令和5年10月1日以降、支払先がインボイス適用事業者ではない場合(免税事業者など)でも、令和11年までの6年間、支払った消費税の80%ないしは50%までは、仕入税額控除の対象になるという経過措置が設けられる予定です。
3.消費税の免税制度(売上1,000万円以下)の適用がうけられなくなる
インボイス制度の適用をうける場合には、売上が1,000万円を超えようが超えまいが、消費税の課税事業者となりますので、令和5年10月1日以降、毎年、消費税の申告と納税が必要になります。売上が1,000万円以下になった年があったとしても、インボイス制度の適用事業者は、消費税の申告と納税が必要になります。
上記の3点が、消費税のインボイス制度開始後の注意点となります。
また、下記リンクにつきましても、あわせて参考にしていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
インボイス制度が始まりますと、これまで免税事業者だった関与先も、一定数は課税事業者になりますし、何より、とくに支払先の請求書等を1つ1つ登録番号等が記入されているかどうかの確認をしなければなりませんので、税理士にとっては、消費税については、大幅に業務が増加することになりそうですね。
本日も、最後までお読みいただきましてありがとうございました。